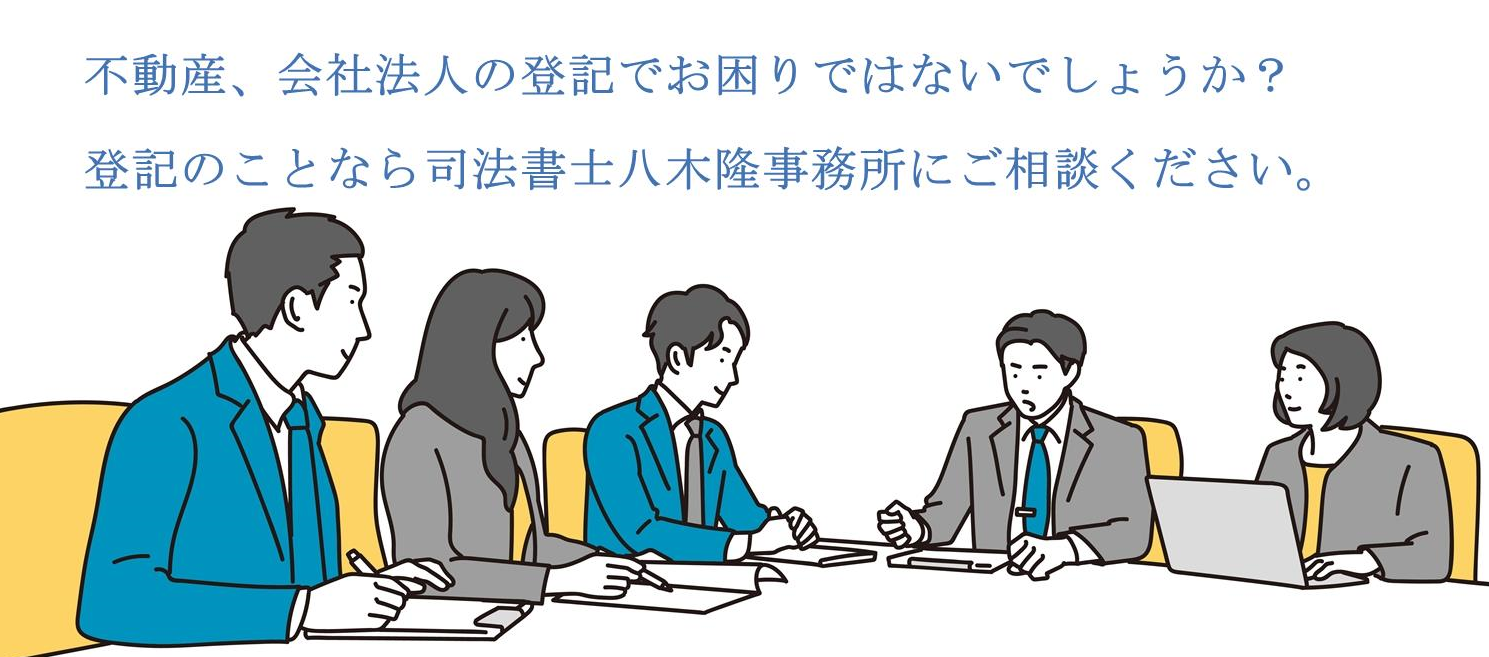
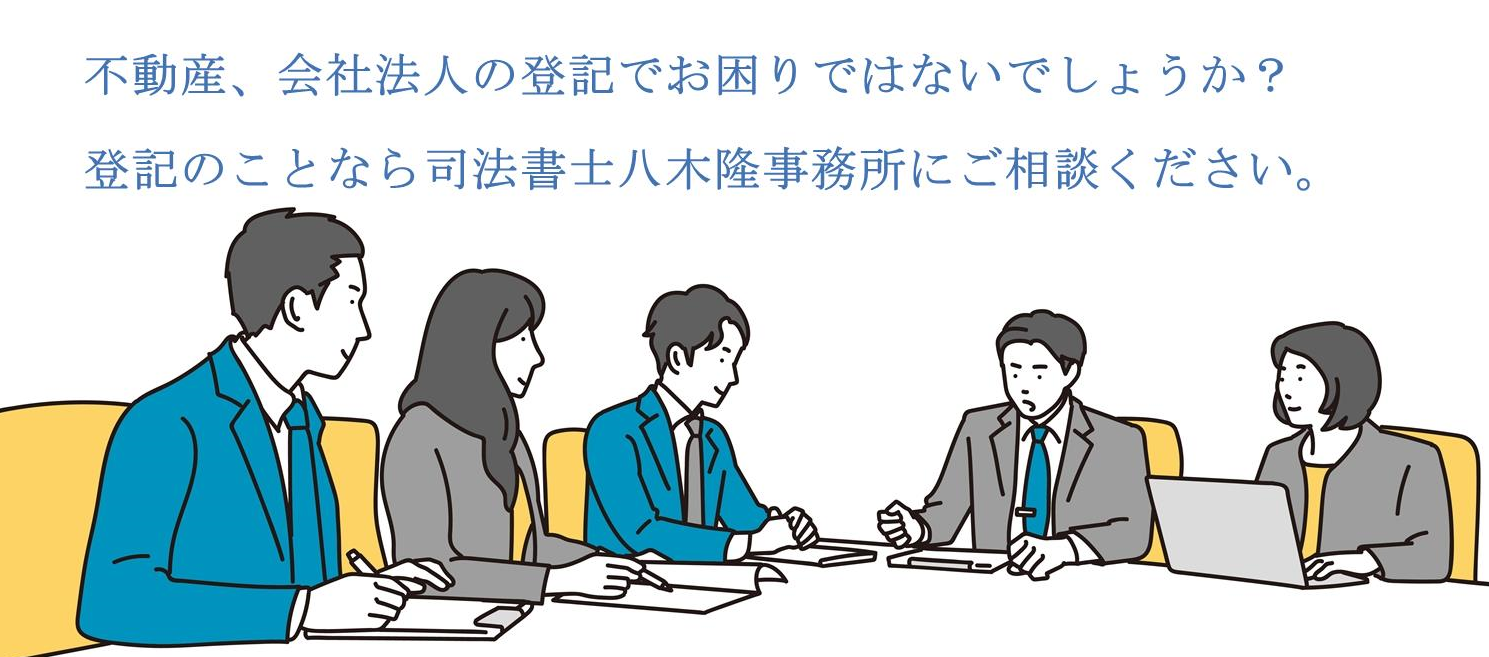
事業承継のための遺言書作成

中小企業にとって円滑な事業承継は重要課題だが・・
中小企業経営者にとって、事業承継は喫緊の課題であると言われています。
しかしながら、多くの中小企業で事業承継が進んでいないのが実情です。
その理由として、そもそも後継者と目する人が存在しないことをあげることができます。
また、後継者はいる者の、何から手を付けて良いか分からず事業承継が後回しになっているケースも多いと言われています。
生前に事業承継を完了していない場合、現経営者の死亡により事業承継を放置していたことによる問題が突然顕在化することになります。
突然の相続発生、そのリスクとは
現経営者が生前に何ら事業承継のための対策を行わずに死亡した場合、現経営者の財産はすべての相続人が法定相続分に応じて共有することになります。
経営者が所有していてた財産は、自社株式であろうと、事業用資産であろうと、それらはすべて相続財産であり、後継者以外の相続人も権利を有することになります。
後継者が、引き続き事業を継続するのであれば、自社株式や事業用資産を後継者である相続人に集中する必要があるのですが、そのためには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割は相続人全員の合意が必要になります。
相続人の1人でも後継者が単独で自社株や事業用資産を取得することに反対すれば、遺産分割協議は成立しないことになります。
この場合、遺産分割を家庭裁判所に委ねることになります。
家庭裁判所に遺産分割が持ち込まれると、解決までに数年を要することも珍しくはありません。
このような状況では、後継者は安定的に事業を経営することができなくなってしまいます。
このようなリスクがあるにもかかわらず、事業承継が後回しになっているのには、事業承継には検討しなければならないことが多岐にわたり、また税金の問題も絡んでくるので、事業承継をしたくてもなかなか着手することができないのではないでしょうか。
そのような経営者の方には、とりあえず遺言書を作成することを推奨します。
なぜ遺言書を作成すべきなのか
後継者が具体的に決まっているのであれば、「後継者に全財産を相続させる旨」の遺言をとりあえず作成しておくことです。
この遺言を作成しておけば現経営者が突然亡くなるような緊急事態が発生したとしても、遺言の効力により、後継者が自社株式や事業用資産を単独相続することになるので、他に相続人がいたとしても遺産分割協議を行う必要はなく、後継者は会社経営に集中することができます。
遺言書は何度も書き直すことが可能です。
最初に作成した遺言に拘束されることはありませんので、会社の状況の変化に応じて、一度作成した遺言を見直し、書き直すこともできます。
但し、認知症等により遺言能力(遺言を作成することができだけの判断能力)を失った後は、書き直しはできないことは留意しておく必要があります。
このようなシンプルな遺言であっても作成しておけば、現経営者に突然相続が発生したとしても、最悪の事態は避けることができます。
遺留分の侵害
なお、後継者に全財産を相続させると、通常他の相続人の遺留分を侵害することになるので、後継者が遺留分侵害額請求を受けた場合に、後継者が遺留分侵害金を他の相続人に支払えるように、その原資を確保しておくための方策は、別途検討しておく必要はあります。
遺言といった予防策を講じた上で、事業承継税制や各種特例の適用の有無等を検討しながら、本格的な事業承継対策に取り組んでみてはどうでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか?
では、遺言を作成することを決めた場合、どの形式の遺言を作成するのがよいのでしょうか。
遺言の代表的な方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言のメリットは思い立ったらすぐにでも作成することができるところです。
紙とペンと印鑑があれば法的に有効な遺言を作成することができます。
デメリットとしては法律にある程度精通していないと無効な遺言を作成してしまう危険がある点です。
より確実な遺言の作成を望むのであれば、公証人が作成する公正証書遺言を選択すべきです。
ただし、公正証書遺言を作成するには、時間と費用がかかります。
今後、遺言を書き直すことを前提に遺言を作成するのであれば、自筆証書遺言を選択しても良いでしょう。
また、令和2年7月10日から始まった法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、紛失、発見されない等の自筆証書遺言のリスクを軽減することができます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| 遺言書作成着手から完成までの時間 | 即時 |
着手から完成まで時間がかかる |
| 遺言書作成に要する費用 |
かからない。 |
公証人手数料がかかる。 |
| 書き直し(遺言撤回)の可否 | 可能 | 可能 |
