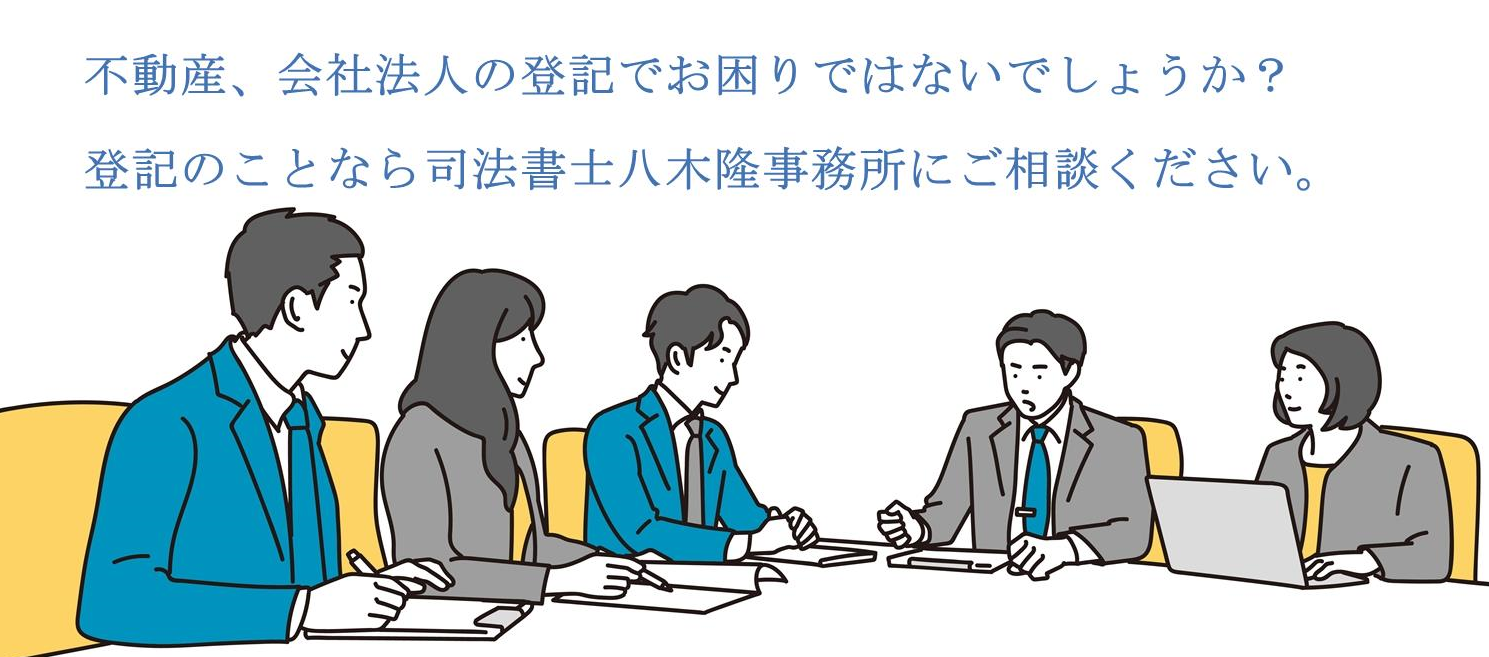
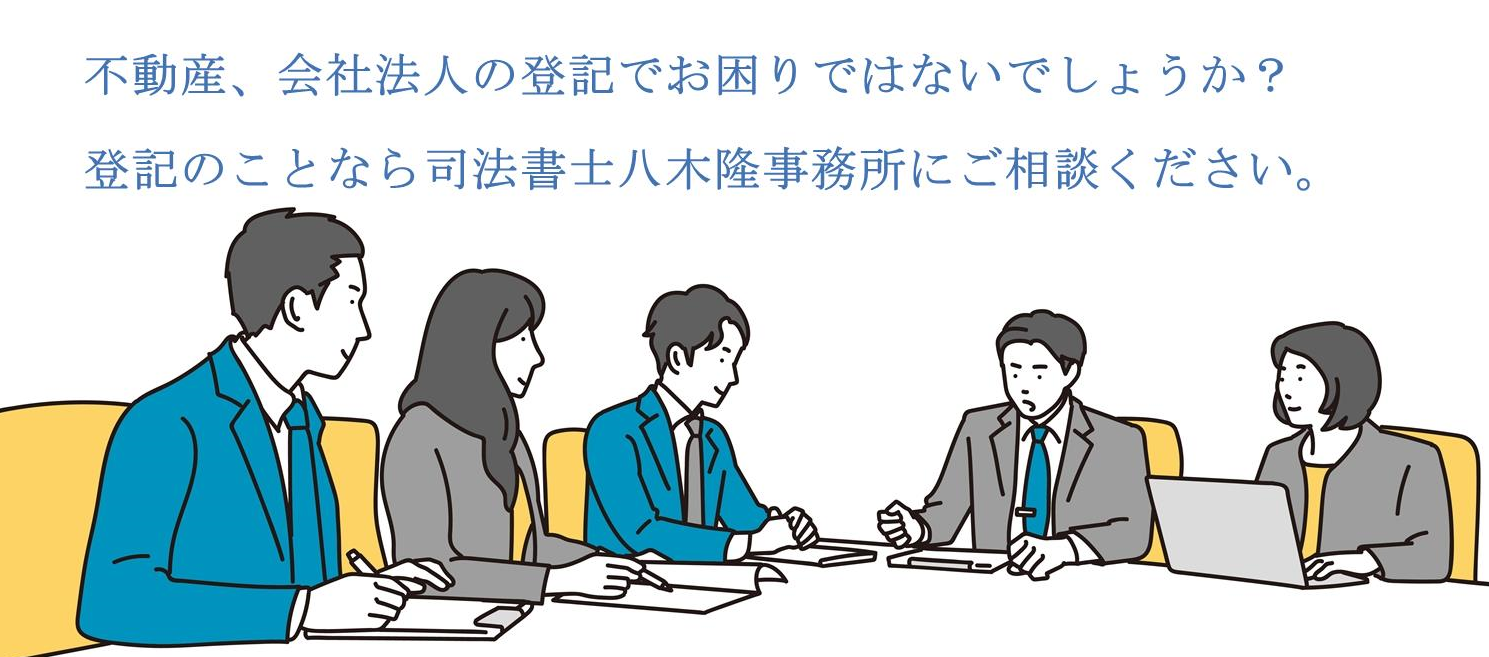
非営利型の一般社団法人の要件
法人税法上、一般社団法人は、非営利型一般社団法人と非営利型以外の一般社団法人に分類することができます。
非営利型一般社団法人は、税法上の公益法人等に該当するため、収益事業を行っている場合、その所得に対してのみ法人税が課税されます。よって、会費収入や寄付金収入等、収益事業によらない所得に対しては非課税扱いとなります。
非営利型以外の一般社団法人は、税法上、普通法人として扱われますので、全ての所得に対して法人税が課税されることになります。
①非営利型一般社団法人
⇒公益法人等
⇒収益事業による所得のみに課税
②非営利型以外の一般社団法人
⇒普通法人
⇒全所得に対して課税
非営利型一般社団法人については、行政庁の認定手続きはありませんので、以下のすべての要件に該当すれば法人税法上の公益法人等として取り扱われることになります。
非営利型一般社団法人は、その要件の違いにより「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の類型があります。
非営利性が徹底された法人の要件
非営利性が徹底された法人とは、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして以下の要件のすべてを満たす一般社団法人をいいます。
①定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
②定款に解散したときは、その残余財産が国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
1・公益社団法人又は公益財団法人
2・学校法人、社会福祉法人等、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人
③上記①及び②の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
(非営利性が徹底された法人の要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配もしくは引き渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)
④各理事(各清算人を含む。)について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
共益的活動を目的とする法人
共益的活動を目的とする法人とは、その会員からの会費により会員共通の利益を図るための事業を行う法人でその事業を運営するための組織が適正である以下の要件のすべてを満たす一般社団法人をいいます。
①会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
②定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
③主たる事業として収益事業を行っていないこと。
④定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
⑤定款に解散したときは、その残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと。
(国若しくは地方公共団体、認定法第5条17号に掲げる法人又は類似の目的を有する一般社団法人又は一般財団法人は除く。)
⑥共益的活動を目的とする法人の要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
⑦各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
非営利型一般社団法人を設立する場合の手続き
1 定款作成
非営利型一般社団法人を設立する場合、定款には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める定款記載事項の他、次の事項を定める必要があります。
非営利性が徹底された法人
定款に記載しなければならない事項
①剰余金の分配を行わない旨の定め
(剰余金の分配の禁止)
第○条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
②解散したときは、その残余財産が国もしくは地方公共団体又は認定法第5条17号に掲げる法人に帰属する旨の定め
(残余財産の帰属)
第○条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
定款に記載してはいけない事項
①理事の員数を2名以下とする定め
②各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える定め。
共益的活動を目的とする法人
定款に記載しなければならない事項
①会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする旨の定め
②会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定め
定款に記載してはいけない事項
①法人の主たる事業として収益事業を行う旨の定め。
②特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定め。
③法人が解散したときは、その残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定め。
④理事の員数を2名以下とする定め
⑤各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1を超える定め。
非営利型一般社団法人を設立するには理事3名以上が必要
非営利型一般社団法人の要件の一つに「各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は三親等以内の親族その他のその理事を一定の特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。」があるため、同族理事の数は3分の1以下でなければなりません。
理事の数が1名の場合、同族理事の数が100%、理事の数が2名の場合、そのうち1名が同族以外の者であったとしても同族理事の数は2分の1(3分の1超)ですので、いずれも同族理事の数が3分の1を超えてしまいます。
そのため非営利型一般社団法人の場合、少なくとも理事は3名必要になります。(理事の数が1名又は2名の非営利型一般社団法人は認められません。)
2 一般社団法人の設立登記
一般社団法人を設立するには、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請する必要がありますが、非営利型一般社団法人について、通常の一般社団法人の設立登記と何ら変わるところはありません。
公益認定を受けた一般社団法人の場合、その名称中に「公益社団法人」という文字を用いなければなりませんが、非営利型に該当する一般社団法人の場合、その名称中に「非営利型一般社団法人」という文字を用いなければならないといった決まりはありませんが、その名称中に「非営利型一般社団法人」という文字を用いることは可能です。実際、その名称中に「非営利型一般社団法人」という文字を用いた一般社団法人が僅かですが登記されています。
3 税務署への設立届
一般社団法人を設立した場合、設立の日以後2ヶ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりませんが、非営利型一般社団法人を設立した場合については、収益事業を行う場合に限り、上記「法人設立届出書」を提出することになります。
但し、非営利型一般社団法人の場合でも、都道府県(県税事務所)及び市町村(市税事務所)には、「法人設立届出書」を提出する必要があります。
登記のご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木隆事務所へ
登記に関することならどんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ
052-848-8033
2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ
お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)
正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
〒467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所
