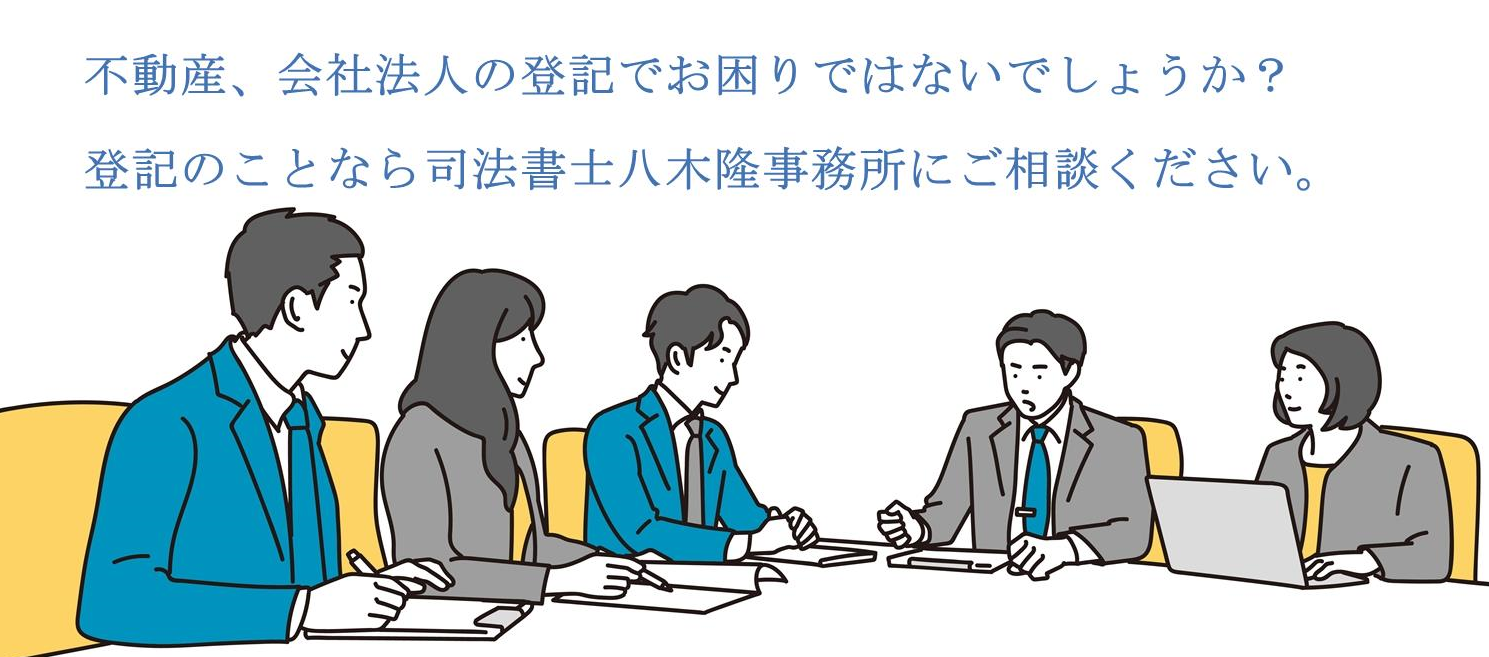
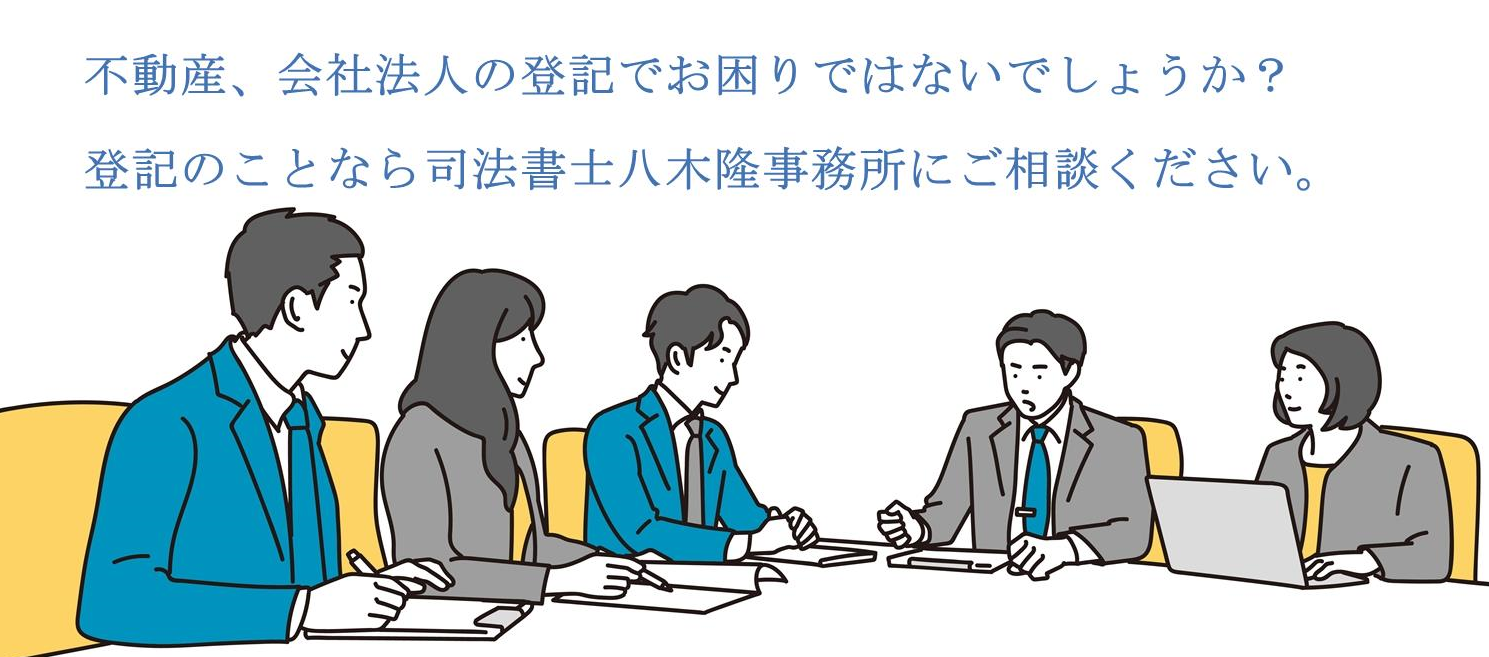
贈与による不動産の名義変更(登記手続)

生前贈与のメリットは、あげたい人、あげたい物、あげたい目的、あげたい時期を、贈与者が自由に決定することができることです。
ただし、認知症になってしまうと生前贈与ができなくなってしまい、保有資産が塩漬け状態になってしまいます。(筑波大学発表の研究報告によると、2025年の認知症の有病者数は約700万人に達するとされています。)
生前贈与を行うには元気なうちに計画的に行う必要があります。
以下では、特に不動産の生前贈与の登記手続きについて登記の専門家である司法書士が解説しています。
不動産の生前贈与の手続き
贈与は、贈与者(贈与する人)の「あげる」という意思表示と、受贈者(贈与を受ける人)の「もらう」という受諾の意思表示が一致することにより成立します。
贈与契約に限ったことではありませんが、契約を締結するには、意思表示ができることが前提になりますので、認知症等により有効な意思表示ができない者は、生前贈与することができません。
生前贈与は元気なうちに計画的に行う必要があります。
贈与契約書等を作成する
贈与契約は、口頭による合意(口約束)だけでも有効に成立し、贈与契約書等の書面の作成は必須ではありませんが、不動産贈与の場合、登記手続き(不動産の名義変更)の関係上、贈与契約書等の書面の作成が必要になります。
権利の登記の申請には『登記原因証明情報』の提供が必須とされています。
『登記原因証明情報』とは、登記原因となる事実又は法律行為の存在を証することを内容とする書面であり、贈与契約書も登記原因証明情報に該当します。
不動産登記事項証明書の取得
贈与する不動産について、正確に記載するため、最寄りの法務局で不動産登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書は法務局の窓口で交付請求するほか、郵送によっても請求することが可能です。
【不動産贈与契約書記載例】
贈与契約書
令和 年 月 日
受贈者○○市○○町○丁目○番地
法務太郎 印
贈与者○○市○○町○丁目○番地
法務花子 印
上記当事者間において、本日下記のとおり贈与契約を締結した。
贈与者法務花子の所有に係る後記不動産を受贈者法務太郎に贈与することを約し、法務太郎これを受諾した。
上記の契約の成立を証するため、この証書2通を作成し、贈与者及び受贈者において、各1通を保有する。
不動産の表示
土地
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 ○○.○○平方メートル
上記不動産贈与契約書は必要最低限を記載したものであり、それぞれの合意内容に応じて作成する必要があります。
贈与契約書には少なくとも、誰(贈与者)が誰(受贈者)に対してどの不動産(不動産の表示)を贈与したのか及び当該不動産の所有権が移転した年月日(贈与契約日)を記載する必要があります。
押印する印鑑
登記手続き上は、認印による押印でも問題ありませんが、契約書の真正を担保し証拠保全を図るためには、実印で押印するのが望ましいでしょう。
印紙税
贈与契約書は課税対象文書に該当し、記載金額のないものとして200円の収入印紙を贈与契約書に貼付します。
貼付した印紙は消印する必要があります。
消印に使用する印鑑は契約書に押印した印鑑でなくても問題なく、押印でなく署名でも問題ありません。
消印するのは、贈与者及び受贈者の双方でも、どちらかの一方でも差し支えありません。
報告形式の登記原因証明情報
贈与契約書の作成に代えて、登記申請用の報告形式の登記原因証明情報を作成して提出することもできます。ただし、登記申請用として作成された報告形式の登記原因証明情報は原本還付ができないので、登記用及び契約当事者の数分だけ作成したほうがいいでしょう。
【報告形式の登記原因証明情報の記載例】
登記原因証明情報
1登記の目的 所有権移転
2登記の原因 令和○年○月○日贈与
3当 事 者
権利者 ○○市○○町○丁目○番地
法務太郎
義務者 ○○市○○町○丁目○番地
法務花子
4不動産の表示
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 ○○.○○平方メートル
5登記の原因となる事実又は法律行為
(1)令和○年○月○日、法務花子(以下「乙」とする。)は法務太郎(以下「甲」とする。)に対して上記不動産の表示に記載する不動産(以下「本件不動産」という)を贈与する申込をし、甲は同日これを受諾した。
(2)よって、令和○年○月○日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転した。
令和○年○月○日 ○○法務局 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
受贈者○○市○○町○丁目○番地
法務太郎 印
贈与者○○市○○町○丁目○番地
法務花子 印
登記名義の変更手続き(贈与による所有権移転登記)
不動産を贈与した場合、登記名義を贈与者から受贈者へ変更する手続きが必要になります。
名義変更の手続きは、贈与した不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に、贈与者と受贈者が共同して申請します。
登記名義の変更を行っておかないと、贈与者が死亡したときに、贈与された不動産の帰属について(相続財産かどうか)相続人の間で争いになることが考えられますので、贈与を受けた者はきちんと登記を備えておくべきです。
以下では登記名義の変更に必要な手続きを解説します。
登記手続に必要な書類等を準備する。
登記手続きを行うには、いろいろな書類等が必要になります。
登記手続きに必要となる書類等を下記の表のとおりです。役所に何度も足を運ばないように、効率よく収集しましょう。
【不動産贈与に必要な書類】
| 必要書類 | 取得場所 | 備考 | |
| 贈与者(贈与する人) | 印鑑証明書 | 市町村役場、区役所 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| 登記識別情報通知書又は登記済権利証 | 贈与者が保管 | ||
| 住民票又は戸籍の附票 | 市町村役場、区役所 | 贈与者の登記上の住所と現住所が異なる場合に必要 | |
| 戸籍謄本等 | 市町村役場、区役所 | 贈与者の登記上の氏名と現氏名が異なる場合に必要 | |
| 固定資産税評価証明書 | 市町村役場、区役所、市税事務所 | 申請する年度のもの | |
| 受贈者(贈与を受ける方) | 住民票の写し | 市町村役場、区役所 | 有効期限はないが現住所が記載されているもの |
| 戸籍謄本等 | 市町村役場、区役所 | 未成年者が贈与を受ける場合、親権者の記載があるもの | |
| その他 | 不動産登記事項証明書 | 法務局 | 贈与物件を調査確認するため |
※赤字は、贈与による登記手続きに必ず必要となる書類
登記識別情報又は登記済権利証は原則必要ですが、紛失等により提出できない場合でも登記申請は可能です。
贈与による所有権移転登記を申請する
贈与契約書の作成が完了し、必要な書類が揃いましたら、管轄の法務局に登記申請いたします。
登記申請は、贈与者と受贈者の双方が申請人になります。
登記申請書を作成する
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和○年○月○日贈与
権 利 者 ○○市○○町○丁目○番地
法務太郎 印
義 務 者 ○○市○○町○丁目○番地
法務花子 印
添付情報
登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報(不動産贈与契約書等のこと)
代理権限証明情報(委任状のこと)印鑑証明書 住所証明情報(住民票の写しのこと)
登記識別情報の登記所での交付を希望します。
令和○年○月○日申請 ○○法 務 局
連絡先の電話番号00−0000−0000
課 税 価 格 金2,000万円
登録免許税 金40万円
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅 地
地 積 ○○○・○○平方メートル
上記は登記申請書の記載例ですので、実際に作成するときは、実情に応じた申請書を作成する必要があります。
義務者(贈与者)は必ず実印で押印する必要があります。
登記申請書を提出する
管轄法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。
提出の方法は法務局に持参する又は郵送する方法が認められています。
登録免許税を納付する
登記申請の際、登録免許税を納付する必要があります。
贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は固定資産税評価額の2%です。
固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書、納税通知書等によりその額を確認することができます。
固定資産税評価額2,000万円の不動産を贈与した場合の登録免許税の額は40万円になります。
登録免許税は、登記申請書に登録免許税相当額の収入印紙を貼り付けて納付するのが一般的です。
貼付した収入印紙には消印をしないように注意してください。
登記識別情報が通知される
登記申請が受理され、無事完了すると受贈者に登記識別情報(12桁の英数字)が通知されます。
登記識別情報が記載された通知書が作成交付されます。
今後、不動産を売却したり担保を入れたりするときの登記申請の際、通知された登記識別情報を提供する必要があります。
登記手続きは司法書士に依頼することができます。
登記申請には、正確な法律の知識と経験を必要とします。
ご自身で登記をなさる場合、登記に関することをいろいろ調べたり、法務局に相談に行ったりする必要があるかと思います。
このようなことが煩わしいと思われる方、確実に登記名義の変更をなさりたい方は、司法書士に依頼することをお勧めします。
当事務所の手数料(司法書士への報酬)
当事務所に不動産贈与による所有権移転登記代理手続きを依頼した場合の、手数料の額の目安
33,000円〜
司法書士へのお問い合わせ
司法書士八木事務所では、不動産贈与による所有権移転登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
不動産を贈与する場合、特に贈与税の負担が、心配になると思いますが、提携する税理士を紹介することもできますので、安心してお問い合わせください。
お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ
052-848-8033
2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ
お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)
正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
〒467−0056
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所
