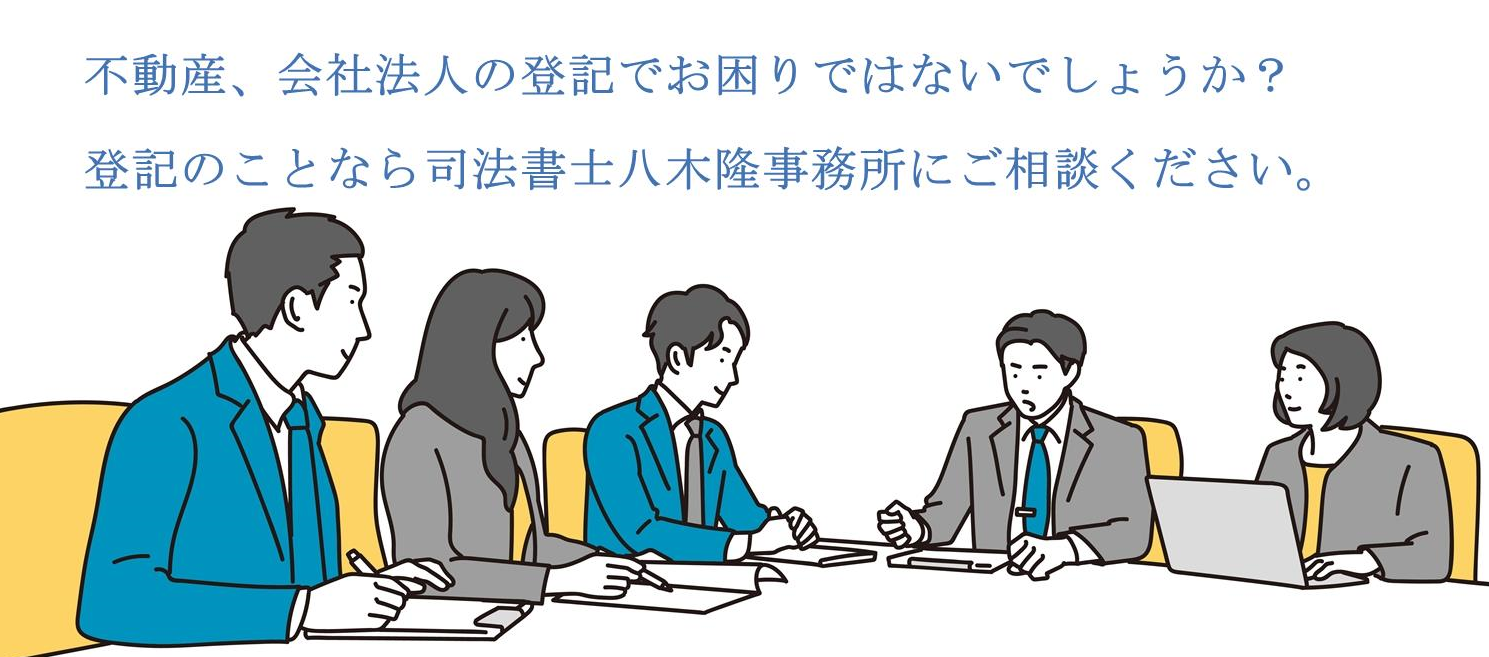
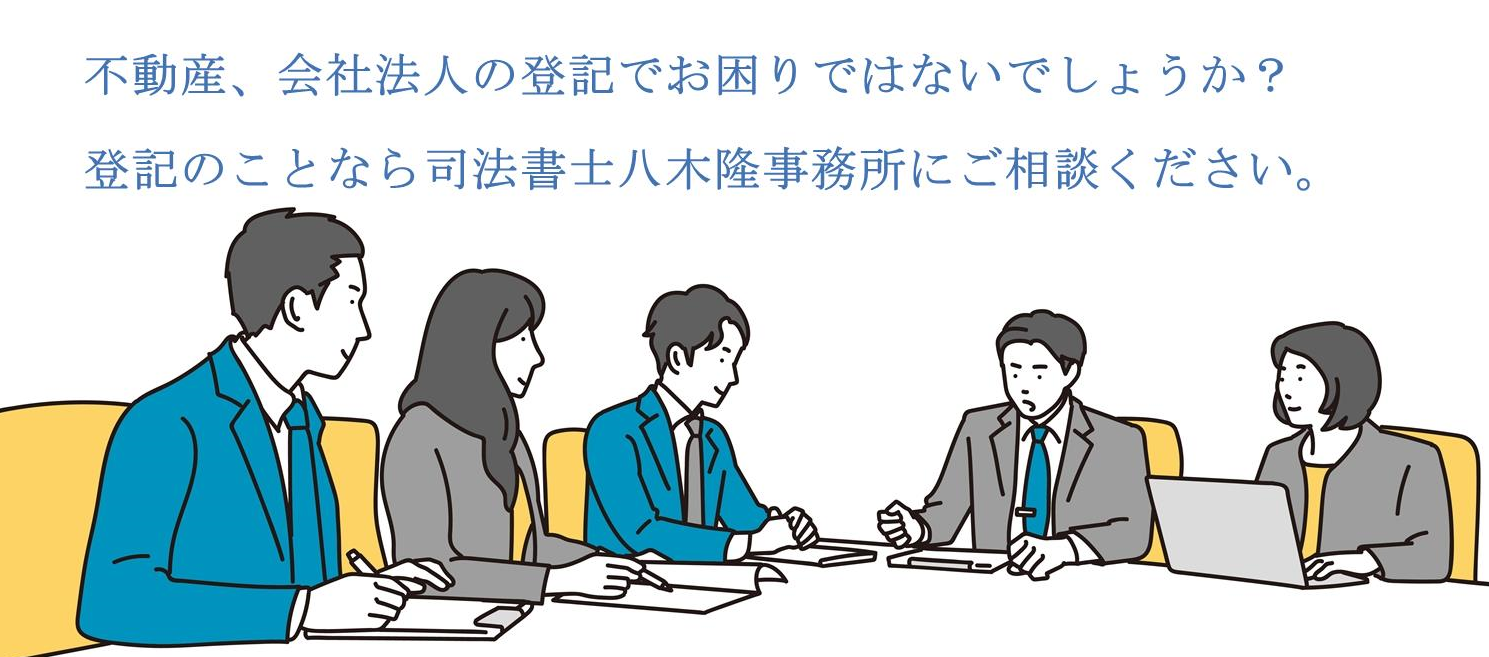
�����؏��⌾�̍쐬
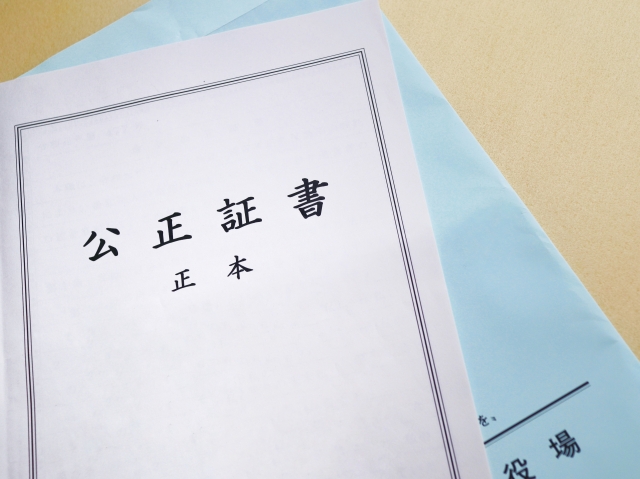
�⌾�ɂ́A���ʕ����̈⌾�Ƃ��āA���M�؏��⌾�A�����؏��⌾�y���閧�؏��⌾�̂R��ނ̕���������܂��B
�����ł́A�����؏��⌾�ɂ��āA������܂��B
�����؏��⌾�Ƃ�
�����؏��⌾�͌��ؐl���쐬����⌾�ł���A���@����߂�ȉ��̕����ɂ��쐬����܂��B
�@�@�ؐl��l�ȏ�̗�������邱�ƁB
�A�@�⌾�҂��⌾�̎�|�����ؐl�Ɍ������邱�ƁB
�B�@���ؐl���A�⌾�҂̌��q��M�L���A������⌾�ҋy�яؐl�ɓǂݕ������A���͉{�������邱�ƁB
�C�@�⌾�ҋy�яؐl���A�M�L�̐��m�Ȃ��Ƃ����F������A�e������ɏ������A����������ƁB�������A�⌾�҂��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�́A���ؐl�����̎��R��t�L���āA�����ɑウ�邱�Ƃ��ł���B
�D���ؐl���A���̏؏��͑O�e���Ɍf��������ɏ]���č�������̂ł���|��t�L���āA����ɏ������A����������ƁB
�����؏��⌾�̃����b�g
�@�@���̐��Ƃł�����ؐl���⌾�쐬�Ɋ֗^����̂ŁA�����̕s���ɂ��⌾�������ƂȂ�����A�⌾���e�̉��߂ɋ^�`�������邱�Ƃɂ�鑊���l�Ԃ̕������̃��X�N�̔���������ł���B
�A�⌾�����{�����ؖ���ɕۊǂ����̂ŁA�⌾���̕����A�B���A�ϑ����̃��X�N������ł���B
�B�����؏��⌾���쐬����ƁA���ؖ���̈⌾�����V�X�e���ɓo�^�����̂ŁA�����l�͈⌾���쐬�̗L����e�Ղɒ������邱�Ƃ��ł��A�⌾�������s����Ȃ��Ƃ��������X�N���y�����邱�Ƃ��ł���B
�C�����؏��⌾�����s����ɂ͉ƒ�ٔ����̌��F���s�v�ŁA�v���Ȉ⌾���s���\�ɂȂ�B
���M�؏��⌾�̏ꍇ�A�����؏��⌾�̏�L�@����C�̃����b�g�����邱�Ƃ��ł����t�Ƀf�����b�g�ɂȂ�܂��B�������A�ߘa�Q�N�V���P�O���ɊJ�n�����u�@���ǂɂ�鎩�M�؏��⌾�̕ۊǐ��x�v�𗘗p����A�����؏��⌾�̃����b�g�̈ꕔ�i�A�A�C�j�����邱�Ƃ��ł��܂��B
���M�؏��⌾�ɔ�����؏��⌾�͈��S�m���Ȉ⌾�����ł���A�⌾�����쐬����ꍇ�A�����؏��⌾����������܂��B
�����؏��⌾�̃f�����b�g
�@���ؖ���ɏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�A�⌾�쐬�ɔ�p�i���ؐl�萔���j��������B
��L�@�Ɋւ��āA�O�o������Ō��ؖ���ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ���A�⌾�҂��w�肷��ꏊ�i�����a�@�j�ɏo�����Ă��炤���Ƃ��ł��܂��B�������A���ؐl�萔�������z����ʓr�����S���Ȃ���Ȃ�܂���B
�����؏��⌾�쐬�̎���
���ۂɌ����؏��⌾���쐬����ꍇ�̎葱�̗����������܂��B
�����؏��⌾�쐬�̎��O����
�܂��́A�����؏��⌾�̊�ƂȂ�⌾�����Ă��쐬���܂��B
�⌾���̍쐬�ɂ́A�@�I�Ȓm�����K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�⌾�������č쐬�̒i�K�Ő��Ƃ̎x�����邱�Ƃ𐄏����܂��B
�⌾�������Ă��o�����܂�����A�Ŋ��̌��ؖ���ɘA������ꂽ��A�⌾�����Ă��e�`�w���ɂ����ؖ���ɑ��t���܂��B
�����؏��⌾�͑S���̌��ؖ���ō쐬���邱�Ƃ��ł��܂��B
���O�ɁA���ؖ���Ō����؏��⌾�쐬�̑��k���Ŏ邱�Ƃ��ł��܂��B
���ؖ���ő��k����Ƃ��́A�\�Ă�����ؖ���ɍs���悤�ɂ��܂��傤�B
�����؏��⌾�̍쐬�ɂ́A�T�ˈȉ��̏��ނ��K�v�ɂȂ�܂����A���ۂɌ����؏��⌾���쐬����ꍇ�́A�쐬������ؖ���ɕK�v�ȏ��ނ����m�F���������B
�K�v���ނ́A�⌾�����Ăƈꏏ�Ɍ��ؖ���ɑ��t����̂���ʓI�ł��B�i���̒i�K�ł̓R�s�[�ł��\���܂��B���̏ꍇ�A�����؏��⌾�쐬�����Ɍ��{�����Q���܂��B�j
�K�v����
�@�⌾�Җ{�l�̈�ӏؖ����i�R�����ȓ��̂��́j
�A���Y���擾����҂Ɋւ��鏑��
�@�E�����l�Ɏ擾������ꍇ
�@�@�⌾�҂Ɛ��葊���l�̑�����������ːГ��{��
�@�E�����l�ȊO�̎҂Ɏ擾������ꍇ
�@�@�Z���[�i���҂��l�̏ꍇ�j
�@�@�o�L�����ؖ����i���҂��@�l�̏ꍇ�j
�B���Y�Ɋւ��鏑��
�@�E�s���Y���擾������ꍇ
�@�@�s���Y�o�L�����ؖ����y�ьŒ莑�Y�ŕ]���ؖ����i�[�Œʒm���ɓY�t���ꂽ�ېŖ������j
�@�E�a�������擾������ꍇ�i���Z�@�ցE�x�X�E���������ʂɓ��肷��ꍇ�j
�@�@�ʒ��̃R�s�[
�C�ؐl�Ɋւ��鏑��
�@�ؐl�̉^�]�Ƌ��̃R�s�[
�D�⌾���s�҂Ɋւ��鏑��
�@�⌾���s�҂̏Z���[�̎ʂ���
�����؏��⌾�̍쐬�ɂ́A�ؐl�Q�l�ȏ�̗�����K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�ؐl�ƂȂ��Ă����l��p�ӂ��܂��B
���̎҂́A�ؐl�ɂȂ邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�����N��
�A���葊���l�y�ю��ҕ��тɂ����̔z��ҋy�ђ��n����
�B���ؐl�̔z��ҁA�l�e�����̐e���A���L�y�юg�p�l
���i���R�ɊY������҂��ؐl�Ƃ��Č����؏��⌾�̍쐬�ɗ���������ꍇ�A���Y�⌾�͖����ɂȂ�܂��B
�ؐl���p�ӂł��Ȃ��Ƃ��́A���ؖ���ŗp�ӂ��Ă��炤���Ƃ��ł��܂��B
���̏ꍇ�A�ؐl�ɓ������x�����̂��ʏ�ł��B
���g�ŏؐl��p�ӂł��Ȃ��Ƃ��́A�\�ߌ��ؖ���ɏؐl�̗p�ӂ����肢���Ă����܂��傤�B
����A���ؖ��ꂩ������؏��⌾�̌��Ă��e�`�w���ɂ�著�t����܂��B
�����؏��⌾�̌��Ă̓��e���m�F����肪�Ȃ���A�����؏��⌾�쐬����\�܂��B
�����؏��⌾�쐬������
�����͈⌾�҂͎���y�ь��ؐl�萔���i�����j�����Q���܂��B
���ؖ���ɑ��t���Ă��Ȃ��ːГ��{���̕K�v���ނ̌��{������A���̌��{�����Q���܂��B
�쐬�������̎葱�̗���͊T�ˎ��̂Ƃ���ł��B
�܂��A���ؐl���ؐl�Q�l�ȏ�̗���̂��ƁA�⌾�҂̖{�l�m�F���s���܂��B
���̌�A���ؐl���������Ă��������؏��⌾�̌��Ă�ǂݏグ�A�⌾�҂ɂ��̓��e�ŊԈႢ�Ȃ����ǂ����m�F���܂��B
���ؐl���ǂݏグ���⌾���e�ɊԈႢ���Ȃ���A�����؏��⌾�̌��ĂɁA�⌾�҂͏�������i����j���܂��B
���̌�A�ؐl���������܂��B
�⌾�ҋy�яؐl�����������؏����A�����؏��⌾�̌��{�ɂȂ�܂��B
���{�͌��ؖ���ɕۊǂ���܂��B
�⌾�҂ɂ͌����؏��⌾�̐��{�y�ѓ��{����n����܂��B
���̌�A���ؐl��������؏��̌��{�A���{�A�y�ѓ��{�̈Ⴂ�ɂ��āA���{�̕ۑ����Ԃɂ��āA���{���̐������@�ɂ��ē��̐���������܂��B
�Ō�Ɍ��ؐl�Ɍ��ؐl�萔���������Ŏx�����܂��B
�����؏��⌾�̎萔��
�����؏����쐬����ꍇ�A���ؐl�Ɍ��ؐl�萔�����x�����K�v������܂��B
�⌾�������؏��ō쐬����ꍇ���A���ؐl�萔�����K�v�ɂȂ�܂��B
���ؐl�萔���̊z�ɂ��ẮA���ؐl�萔���߂ɂ���߂��Ă��܂�
�����؏��⌾�̌��ؐl�萔���́A�⌾�ɂ�葊���������͈②������Y�̉��z��ړI���z�Ƃ��Čv�Z���܂��B
�e�����l�E�e���҂��ƂɁA�����������͈②������Y�̉��z�ɂ��ړI���z���Z�o���A���ꂼ��̎萔�����Z�肵�A���̍��v�z�����̏؏��̎萔���̊z�ƂȂ�܂��B
�y�����؏��⌾�̎萔���z
| �ړI�̉��z | ||
| �P�O�O���~�܂� | �T�C�O�O�O�~ | |
| �Q�O�O���~�܂� | �V�C�O�O�O�~ | |
| �T�O�O���~�܂� | �P�P�C�O�O�O�~ | |
| �P�C�O�O�O���~�܂� | �P�V�C�O�O�O�~ | |
| �R�C�O�O�O���~�܂� | �Q�R�C�O�O�O�~ | |
| �T�C�O�O�O���~�܂� | �Q�X�C�O�O�O�~ | |
| �P���~�܂� | �S�R�C�O�O�O�~ | |
| �ȉ��A���ߊz�T�C�O�O�O���~���ƂɁA�@�R���~�܂łP�R�C�O�O�O�~�A�A�P�O���~�܂łP�P�C�O�O�O�~�A�B�P�O���~������̂W�C�O�O�O�~���Z | ||
|
�@�⌾���Z |
||
���ؐl�萔���̋�̓I�v�Z���@
�z��҂ɕs���Y�i�Q�C�O�O�O���~�j�A���j�ɗa���i�P�C�O�O�O���~�j�A�����ɗa���i�P�C�O�O�O���~�j�ɑ���������|�̌����؏��⌾���쐬����ꍇ�̌��ؐl�萔���̊z
�z��҂ւ͂Q�C�O�O�O���~�̕s���Y�𑊑�������̂ŖړI�̉��z�͂P�C�O�O�O���܂łƂȂ�萔���̊z�͂Q�R�C�O�O�O�~�A���j�ւP�C�O�O�O���~�̗a���𑊑�������̂ŖړI�̉��z�͂P�C�O�O�O���~�܂łƂȂ�萔���̊z�͂P�V�C�O�O�O�~�A�����ւ͂P�C�O�O�O���~�̗a���𑊑�������̂ŖړI�̉��z�͂P�C�O�O�O���~�܂łƂȂ�萔���̊z�͂P�V�C�O�O�O�~�A���v�Ŏ萔���̊z�͂T�V�C�O�O�O�~�ɂȂ�܂��B
�{���ł͈�Y���z���P���~�ȉ��ł��̂ŁA�⌾���Z�Ƃ��ĂP�P�C�O�O�O�~�����Z����܂��̂ŁA���ؐl�萔���͂U�W�C�O�O�O�~�ƂȂ�܂��B
�z��ҁ@�@�@�@�Q�R�C�O�O�O�~
���j�@�@�@�@�@�P�V�C�O�O�O�~
�����@�@�@�@�@�P�V�C�O�O�O�~
�⌾���Z�@�@�@�P�P�C�O�O�O�~
���ؐl�萔���@�U�W�C�O�O�O�~
�����؏��⌾�쐬�̎����ł́A�s���Y�̉��z�ɂ��ẮA�Œ莑�Y�ŕ]���z��p����̂���ʓI�ł��B
�ړI�̉��z���Z�肷�鎑���Ƃ��āA�Œ莑�Y�ŕ]���ؖ��������o���܂��B
�a�����̖ړI�̉��z�ɂ��ẮA�⌾�쐬���̗a���c������ɎZ�肷��̂���ʓI�ł����A�c�����L�ڂ��ꂽ�ʒ��̃R�s�[�̒�o�܂ł͋��߂��܂���B�i�a�����c���̂��悻�̊z�������œ`����̂���ʓI�ł��B�j
���J��Ɏ҂��w�肵���ꍇ�̎萔��
���J��Ɏ҂Ƃ́A�c��̍��J������s���҂ł���A���J���Y�i�n���A�Ջ�y�ѕ���̏��L���j�����p����҂ł��B
�푊���l�́A���J��Ɏ҂��w�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�w��̕��@�ɂ��ẮA��߂��Ă��܂���̂ŁA�K�������⌾�ɂ��w�肷��K�v�͂���܂��A�����؏��⌾�ɂ����J��Ɏ҂��w�肵���Ƃ��́A���Y�̑������͈②�̎萔���Ƃ͕ʂɁA�P�P�C�O�O�O�~�̌��ؐl�萔�����K�v�ɂȂ�܂��B
�⌾���쐬�Ɋւ��邨�₢���킹
�⌾���쐬�Ɋւ��邱�ƂȂ�ǂ�ȍ��ׂȂ��Ƃł����C�y�ɂ��₢���킹���������B
���₢���킹
1�@���d�b�ɂ�邨�₢���킹�@
�@�@052-848-8033
2�@���₢���킹�t�H�[������̂��₢���킹
���d�b�͕���10������20���܂Ŏt���Ă���܂��B�y���j���͋x�Ɠ��ł����A�������ɂ��鎞�͑Ή��������܂��̂ŁA��x�������ɂȂ��Ă݂Ă��������B
���₢���킹�t�H�[������̂��₢���킹�ɑ��Ă͌���24���Ԉȓ��ɕԐM���܂��B
�i���G�Œ�����v���邨�₢���킹�́A�܂łɂ����Ԃ����Ƃ��������܂��B�j
�����Ȃ��˗��O�ɁA���ώ萔���A���k�����̖��ڂŔ�p�𐿋����邱�Ƃ͈�������܂���̂ŁA���S���Ă��₢���킹���������B
��467�|0056�@
���É��s����攒�����ڂX�Ԓn�@
����n�C�c�S�O�R��
�i�@���m���ؗ�������
