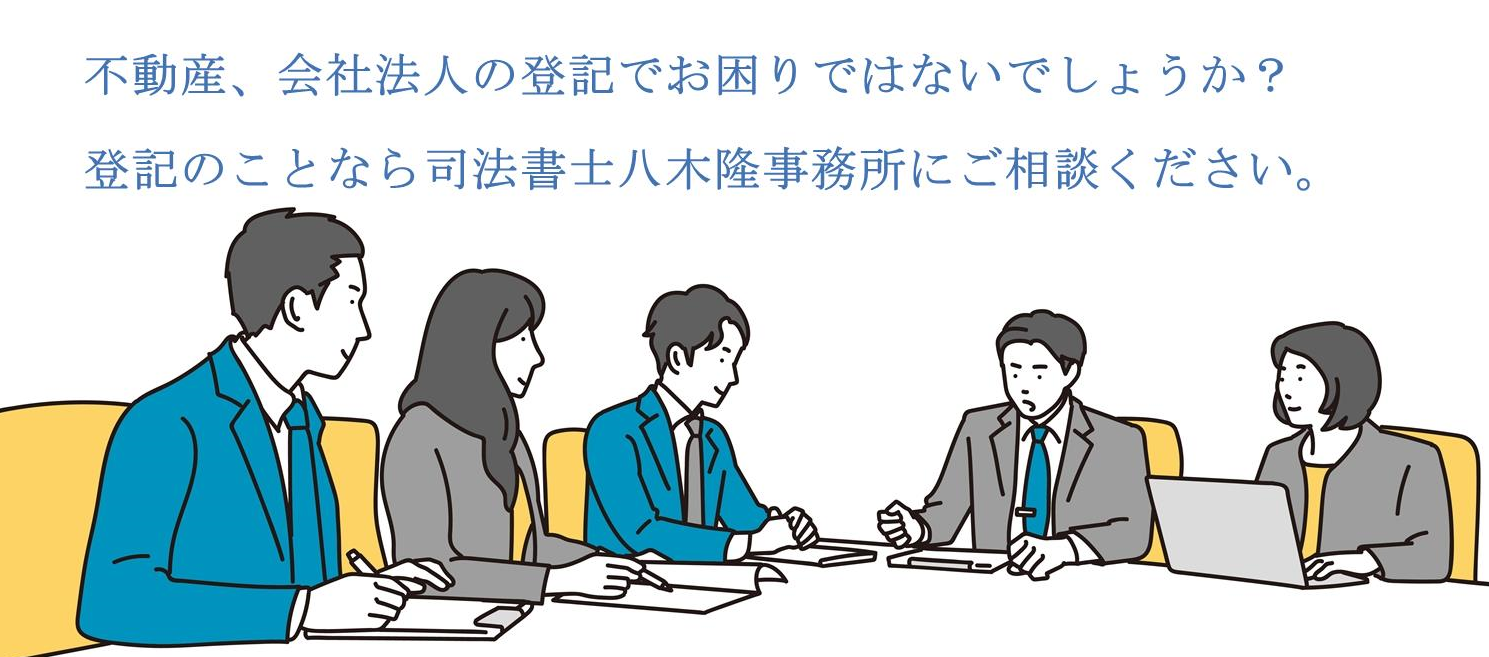
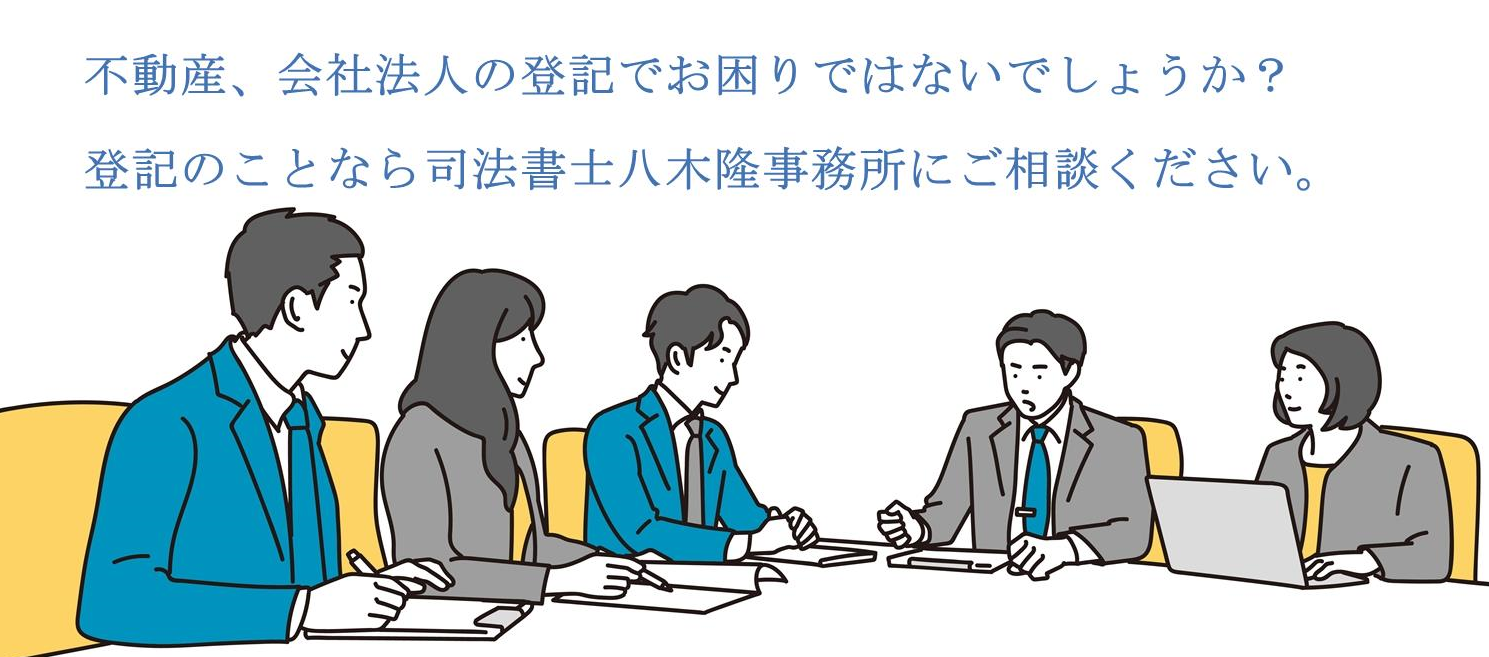
相続登記の申請の義務化について
相続登記の義務化に関する規定を盛り込んだ改正不動産登記法が、令和6年4月1日に施行されます。
この記事では、相続登記の義務化について司法書士が解説いたしております。
相続登記とは
不動産の所有者が死亡した場合に、不動産の登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことを相続登記(相続による所有権移転登記)といいます。
相続登記は、相続により取得した不動産の所在地を管轄する法務局に申請書を提出する方法により行います。
相続登記には、戸籍謄本等や遺産分割協議書等の相続を証する書面等を添付書類として提出する必要があり、登記申請時には、登録免許税を納付する必要があります。
【関連記事】不動産を相続したときの相続登記の手続を司法書士が解説
なぜ相続登記の申請を義務化するのか?
相続登記の任意性(改正前)から義務化(改正後)へ
不動産の権利に関する登記は、私的自治の原則が支配する領域であり、登記申請を行うかどうかは、権利者に委ねられ国家が介入しないことを原則としており、相続登記においてもその申請は任意であり、申請期間も設けられていませんでしたが、令和6年4月1日施行予定の改正不動産登記法により、相続登記の申請については公法上の義務となります。
私的自治の原則とは
私人間の契約や取引は、私人間の自由な意思に委ねられるべきであり、そこに国家が必要以上に介入すべきではないといった考え方のことです。
相続登記を義務化する理由
昨今問題となっている所有者不明土地は全体で約22・2%、その原因の約65・5%が相続登記の放置とされています。
所有者不明土地を解消するためには、相続登記が促進されることの重要性が指摘され、今般、所有者不明土地の発生を防止するための方策の一つとして相続登記の申請を義務化することに相成りました。
相続登記の義務化のポイント
1,相続登記の申請が公法上の義務となる。
2,原則、相続から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
3,申請期間内に正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、過料の制裁あり。
4,相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より開始
(施行日より前に開始した相続にも適用あり)
相続登記の申請義務の基本事項
相続(特定財産承継遺言を含む)または遺贈により不動産を取得した相続人に対して、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が課せられることになります。
また、法定相続分による共同相続登記を行った後に、遺産分割が成立した場合、遺産分割の内容を反映した相続登記の申請義務が追加的に課せられることになります。
相続登記の義務化を具体的な事例を通して検討
事例
・令和6年4月2日、甲土地の所有者(登記名義人)Aが死亡
・亡Aの相続人は、子XとYの2名
・相続人XとYいずれも、相続開始日である令和6年4月2日にAの死亡と甲土地の所有権を相続により取得したことを知ったものとします。(本事例では、令和6年4月2日が、申請期間3年の起算日になります。)
(相続登記の申請期間3年の起算日は、相続人が相続の開始及び相続による不動産の取得を認識した日となりますので、各相続人毎にその起算日が異なることがあります。)
被相続人Aが遺言をしていなければ、XとYは甲土地の所有権を法定相続分に応じて取得することになります。
相続開始によりXおよびYは、各2分の1の割合で甲土地を遺産共有することになります。
X・Yはいずれも相続により所有権を取得した者に該当するので、令和6年4月2日(本事例における起算日)から3年以内に所有権移転登記(相続登記)を申請しなければなりません。
この場合の相続登記は、法定相続分による共同相続登記を申請することになります。
この法定相続分による共同相続登記は、共同相続人全員で申請することも各相続人が単独で申請することができますが、単独申請の場合、自己の相続分のみを登記することはできず、申請人にならない他の相続人全員の相続分も含めた相続登記の申請でなければなりません。
本事例で、X・Yが共同で、または、X又はYが単独で法定相続による共同相続登記を申請したときは、X及びYは、相続登記の申請義務を履行したことになります。
相続登記の申請に代わる相続人申告登記の申出制度とは
改正法では、相続登記の申請義務を簡易に履行させる方策として新たに相続人申告登記の制度を新設しました。
相続人申告登記の申出とは、相続登記の申請義務を負う者が、登記官に自らが相続人である旨を申出ることにより、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされる制度になります。
本事例で、相続人X及びYは、相続人申告登記の申出を行うことにより、法定相続分により共同相続登記を申請しなくても、相続登記の申請義務を履行したものみなされます。
3年以内に、相続人X・Y間で遺産分割協議が成立した場合
令和7年4月2日、相続人X・Y間で、甲土地はXが取得する内容の遺産分割協議が成立
相続人Xの相続登記申請義務
・令和6年4月2日から3年以内に、法定相続分による共同相続登記を申請する義務
⇒相続人申告登記の申出により代替可能
・令和7年4月2日により3年以内に遺産分割協議の内容を反映した相続登記を申請する義務
※法定相続分の取得に係る相続登記の申請義務と、遺産分割による法定相続分を超える持分の取得に係る相続登記の申請義務が併存すると解されます。
・相続人Yの相続登記申請義務
令和6年4月2日から3年以内に、法定相続分による共同相続登記を申請する義務
⇒相続人申告登記の申出により代替可能
相続人Xが遺産分割協議の内容を反映した相続登記を令和6年4月2日から3年以内に申請すれば、相続人XおよびYは期間内に相続登記の申請義務を履行したことになります。
遺産分割協議により不動産を取得する相続人が具体的に決定したときは、法定相続分により共同相続登記を経由することなく、直接、遺産分割協議により不動産を取得した相続人名義に相続登記を申請することが可能です。
法定相続分による共同相続登記を経由しないのが一般的です。
令和6年4月2日から3年以内に、遺産分割協議の内容を反映した相続登記の申請ができない場合、相続人Xは、令和6年4月2日から3年以内に、法定相続分による共同相続登記または相続人申告登記の申出を行うことにより、一旦相続登記の申請義務を履行したことになりますが、遺産分割協議成立の日である令和7年4月2日から3年以内(令和10年4月2日まで)に遺産分割協議の内容を反映した相続登記を申請する義務が残されます。
また、相続人Yは、令和6年4月2日から3年以内に、法定相続分による共同相続登記または相続人申告登記の申出を行うことにより、相続登記の申請義務を履行したことになります
3年以内に、遺産分割協議が成立する見込みがない場合
この場合、令和6年4月2日から3年以内に、相続人X及びYは、法定相続分による共同相続登記または相続人申告登記の申出を行うことにより、相続登記の申請義務を履行したことになります。
令和6年4月2日から3年経過後に、遺産分割協議が成立し、甲土地は相続人Xが取得することになった場合、相続人Xは遺産分割協議成立の日から3年以内に遺産分割協議の内容を反映した相続登記を申請しなければなりません。
遺言書がある場合
相続人Xに甲土地を相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)または、甲土地を遺贈する旨の遺言があった場合
この場合、相続人Xは、何らの行為を要せずに相続開始時(令和6年4月2日)から甲土地の所有権を取得したことになります。
相続人Xは、自己に甲土地を相続させる旨の遺言の存在を認識したときから3年以内に、遺言の内容を反映した相続登記(遺贈であれば遺贈による所有権移転登記)または、相続人申告登記の申出を行うことにより相続登記の申請義務を履行したことになります。
遺贈について
相続人に対して不動産の遺贈があった場合も、受遺者である相続人に対して登記申請義務が課せられています。
また、令和5年4月1日より、相続人に対する遺贈を原因とする所有権移転登記については、受遺者である相続人が単独で申請することが可能になります。
相続登記の義務化への対応(まとめ)
相続登記の義務化への対応(まとめ)
・3年以内に遺産分割が成立したときは、3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請すればOK
諸事情により3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請できないときは、各相続人は、相続人申告登記の申出を行えばOK(但し、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請しなければならない。)
・3年以内に遺産分割が成立する見込みがないときは、3年以内に、各相続人は相続人申告登記の申出を行えばOK(法定相続分による共同相続登記の申請でもOK)
また、3年経過後に遺産分割が成立したときは、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請すればOK
相続登記の申請義務を怠った場合の過料について
法律上(改正不動産登記法)は、正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料に処されることになっています。
過料とは、法律秩序を維持するために、法令に違反した場合(行政手続上の義務違反など)に課せられる行政上の秩序罰であり、犯罪行為を犯した場合に課せられる刑事罰である罰金とは異なるものです。
相続登記の申請義務を怠った場合でも、正当な理由があれば過料は科せられませんが、どのような事情があれば正当な理由となるのかについては、今後通達等で明らかにする予定とされています。
なお、申請期間内の申請を怠った場合であっても、直ちに過料に処されるわけではなく、事前に申請義務の履行の催告がなされ、それに応じて相続登記を申請した場合には、過料には処さない方向での運用が予定されているようです。
相続登記の申請義務化に関する経過措置
相続登記の申請の義務化を盛り込んだ改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されますが、施行日より前に発生した相続に関しても適用されることになります。
施行日より前に発生した相続の場合、申請期間の起算日は、施行日または相続人が相続の開始及び相続による不動産の取得を認識した日のいずれか遅い日から開始することになります。
司法書士へのご相談・依頼をご検討の方へ
司法書士八木事務所では、相続登記(不動産相続による所有権移転登記)に関するご相談、ご依頼を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ
052-848-8033
2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ
お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)
正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
〒467−0056
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所
